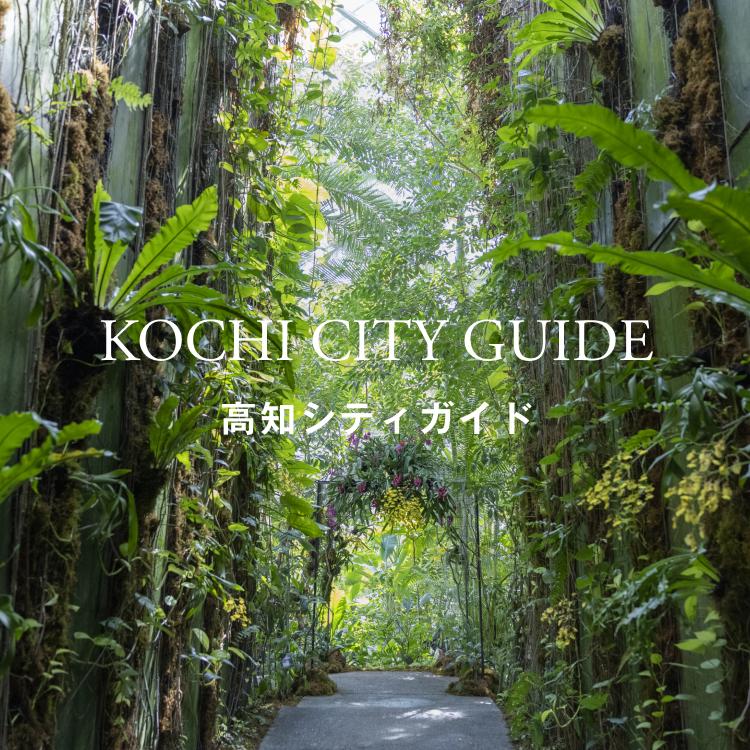FASHION
フリーダ・カーロにとって、着ることはメッセージでした。
『カーサ ブルータス』2019年3月号より
| Fashion, Design | a wall newspaper | photo_Nickolas Muray(portrait), Javier Hinojosa(items) text_Mika Yoshida & David G. Imber ©Diego Rivera and Frida Kahlo Archives, Banco de México, Fiduciary of the Trust of the Diego Rivera and Frida Kahlo Museums
本人が身につけていた衣装や小物が伝える激動の人生と、自己プロデュースの手法とは。
Loading...