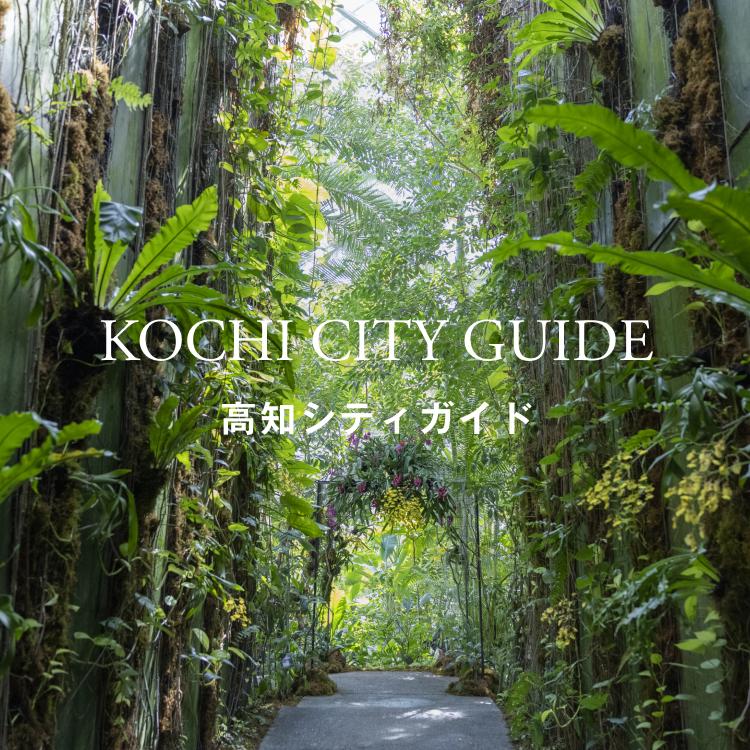CULTURE
大坊勝次の名言「甘みの中の苦みが、背筋を伸ばしてくれる。 これ、コーヒーの…」【本と名言365】
| Culture, Food | casabrutus.com | photo_Yuki Sonoyama text_Yoko Fujimori illustration_Yoshifumi Takeda design_Norihiko Shimada(paper)
これまでになかった手法で新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。閉店から10年を経てもなお、珈琲ファンの間で語り継がれるネルドリップの名店〈大坊珈琲店〉。焙煎と抽出の探求者である店主・大坊勝次氏が綴る、人生訓のように示唆に富んだ焙煎論とは。