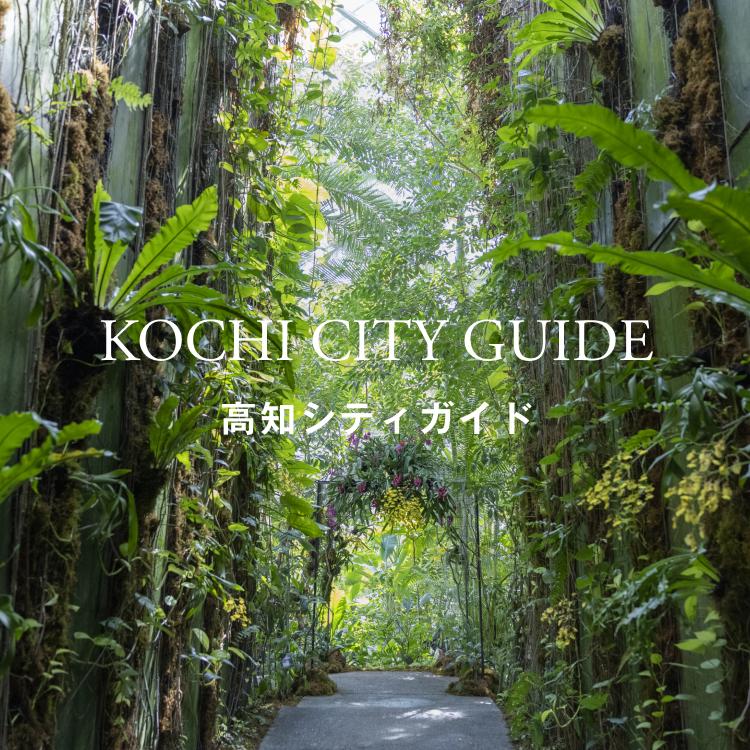ART
【インタビュー】諏訪敦による、「視ること、そして現すこと」への問いと答え。
| Art | casabrutus.com | photo_Kenya Abe text_Hikari Torisawa
硬質さの漂う細密な描法で現代における写実絵画の価値を問い、その変容と拡張に挑む画家・諏訪敦の展覧会『眼窩裏の火事』が、東京〈府中市美術館〉で開催されている。終戦直前に満州へ渡った家族の歴史と記憶を辿るプロジェクト、コロナ禍という制約を逆手にとった静物画の探求、そして90年代から描き、今なお追い続ける舞踏家・大野一雄の肖像などを集めた大規模個展を訪ね、画家に話をきいた。
Loading...
Loading...