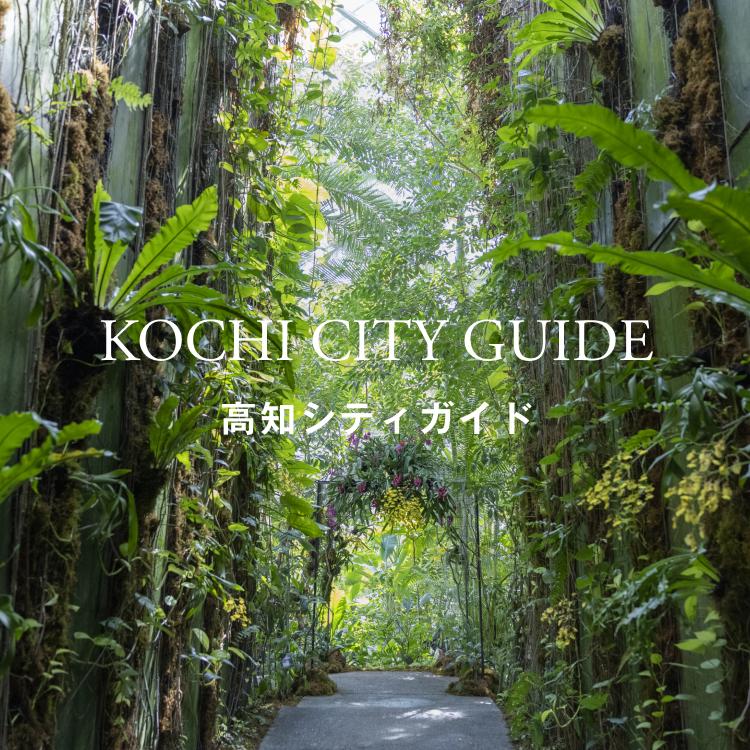CULTURE
槇文彦の名言「建築は、人間と同様、遅かれ早かれ滅びるものですが…」【本と名言365】
| Culture, Design | casabrutus.com | photo_Yuki Sonoyama text_Housekeeper illustration_Yoshifumi Takeda design_Norihiko Shimada(paper)
これまでになかった手法で、新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。丹下健三やホセ・ルイ・セルトらの意思を継ぎ、日本のモダニズム建築を牽引してきた槇文彦。都市と建築の繋がりを観察することで、ヒルサイドテラスなど地域コミュニティを生み出してきた巨匠が見つけた「滅びない建築」とは。