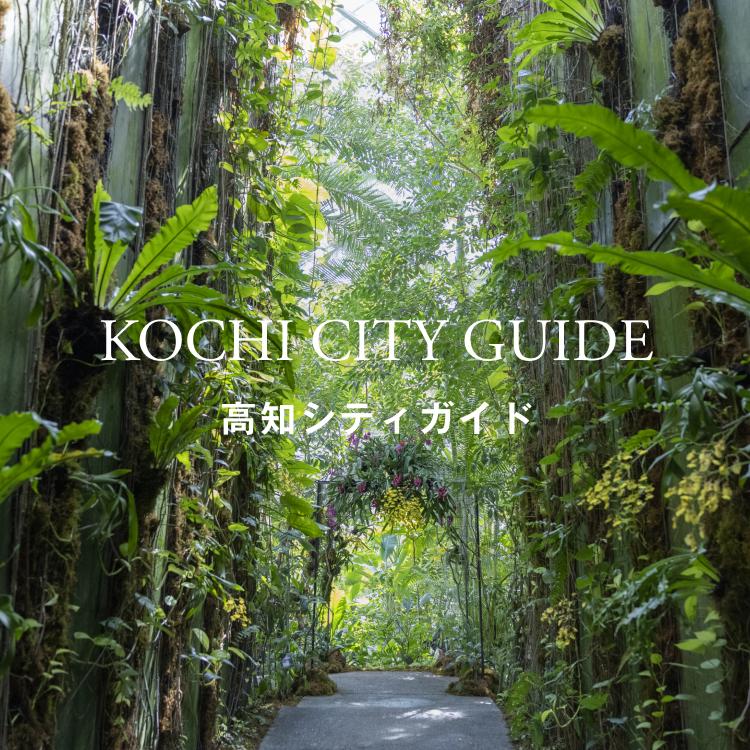CULTURE
【本と名言365】大橋晃朗|「椅子の機能概念というものを、…」
| Culture, Design | casabrutus.com | photo_Miyu Yasuda text_Yoshinao Yamada illustration_Yoshifumi Takeda design_Norihiko Shimada(paper)
これまでになかった手法で、新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。同時代に活躍する建築家たちを魅了し、唯一無二の家具をデザインした大橋晃朗。多くを語らなかった彼が遺した言葉の断片から、哲学をもってデザインに挑み続ける姿勢を追いかけます。