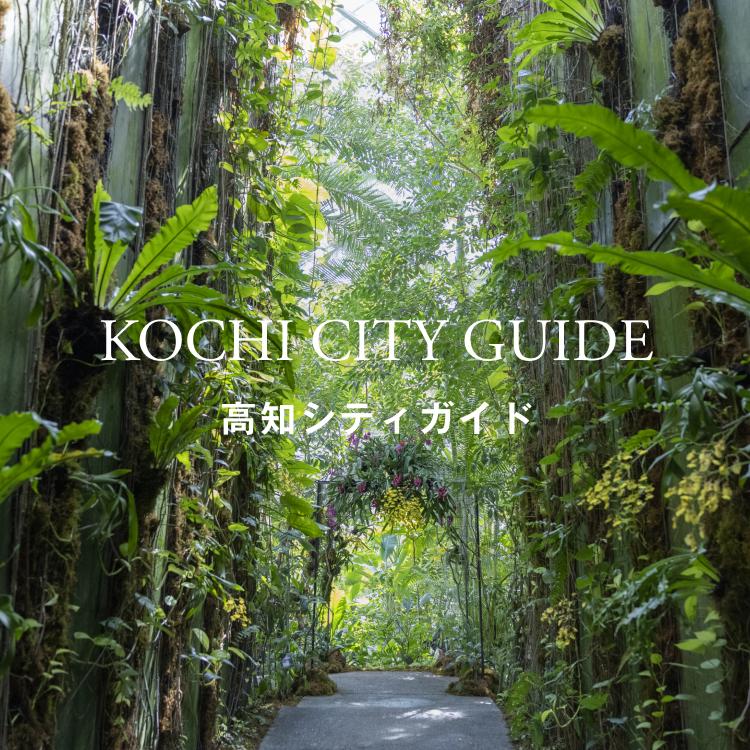CULTURE
岡本太郎の名言「眼は存在が宇宙と合体する穴だ。その穴から…」【本と名言365】
| Culture, Art | casabrutus.com | photo_Yuki Sonoyama text_Keiko Kamijo illustration_Yoshifumi Takeda design_Norihiko Shimada(paper)
これまでになかった手法で、新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。「芸術は爆発だ!」エネルギッシュな作品と発言でいつの時代も人々に影響を与え続ける芸術家・岡本太郎。彼が世界各地の美術と建築を訪ねて、その本質を語った。