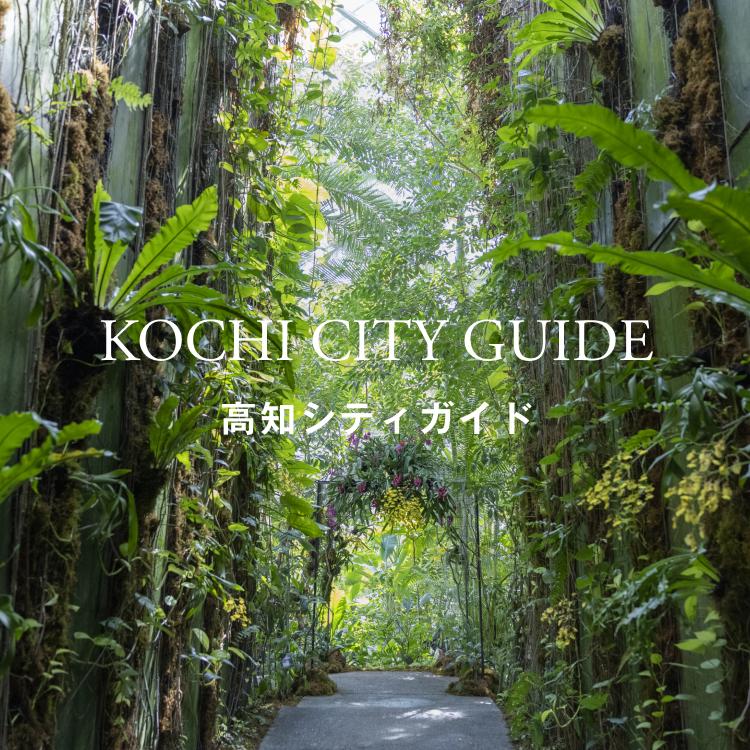CULTURE
原田治の名言「美術は、…」【本と名言365】
| Culture, Art | casabrutus.com | photo_Yuki Sonoyama text_Keiko Kamijo illustration_Yoshifumi Takeda design_Norihiko Shimada(paper)
これまでになかった手法で新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。「OSAMU GOODS®(オサムグッズ)」の生みの親であり、希代の美術ファンであり、多くのエッセイをのこす原田治が語った美術について。
Loading...